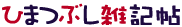GBLシーズン15でACE到達

ポケモンGOの対人戦GOバトルリーグ。シーズン15「隠された宝石」シーズンでACE到達。
昨日、ランク20までの規定の勝利数を達成してもらった初期レートが1953。前シーズンの初期レートが1900ぐらいだったので、けっこうもらえた。
今シーズンのスーパーリーグというレギュレーションは、技変更などがあって前シーズンとは環境が激変。前シーズンが決まりきったテンプレパーティばかり出てきて、今イチ面白みに欠けたのことを考えると、今シーズンはパーティのバリエーションが豊富でかなり面白い。
いちいち一試合ごとに右往左往ジタバタすることになって負けが込むことも多かったんだけど「あーでもないこーでもない」が面白いんでスマホを投げるようなことにはならなかった。かな。
とりあえず。今シーズンも目標はこれで達成。まだまだシーズンは続くので、面白いゲームができればいいなあ、と。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
みけさん永眠


みけさんが亡くなった。
2023/6/6 15:00 27歳
(写真は6/5早朝、ベッドに飛び乗ってきたところを撮影)
今まで本当にたくさん、言い尽くせないほどたくさん、本当にありがとう。
これからゆっくり休んでください。
2023/6/10
一之江の城東動物霊園で荼毘にふしてもらってきた。
2008/2/7に23歳で亡くなったホームズ
2010/1/4に12歳で亡くなったちー
と同じ霊園。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
WORDをテキスト保存した時のルビの捕捉

いや、あいかわらず雑なネタ。
.docx、ワードファイルではなくて、ワード文書を書式なしテキストで保存したテキストデータがたまにやってくる。基本的にシンプルなものが多くて流れ作業で済む。
…なんだけど、ルビのついたものがたまにあるのでその対応のメモ。
ワードの文書を書式なしtxtで書き出すとルビは
「これは漢字(かんじ)にルビがつく」
などと、ワード文書ではルビのところが、漢字と半角カッコでくくられたルビにわけられて保存されることになる。
そういや、以前もこんなことあったなあと思い出して、この雑記帖を検索したら出てきたのが
青空文庫のルビや傍点をHTMLタグに変換
https://t2aki.doncha.net/?id=1443167217
↑このエントリ。
青空文庫で使われている、青空記法は多くのひとに使われるように、よく練られているなあ、と感心した記事で、やっぱりさきほども改めて感心。
てことで、その時の記事からほぼ流用したのが以下のスクリプト。
perlで、Unicodeブロックを使った正規表現で漢字やかなを拾えるんで大助かり。
ただ、こいつはビミョーで、漢字に続いて半角カッコがあるのは、ワードが吐き出したルビだけとは限らないし、ルビの対象となる漢字の範囲がこれだけだと特定できない。
青空記法では問題にならないんだけど、ワードの吐き出しに多くは求められない。
なので、あくまでも初校作成時の手助け程度、かな。
にしても。
まだ5インチと3.5インチのフロッピーディスクが現役で、MSDOSは3.0が出た頃、NECの98シリーズが人気だった頃だからもう40年近く前の昭和の頃。日本ダービーでシンボリルドルフが皇帝になった頃。
Wizardryというゲームがやりたくてパソコンを買って、その後競馬データをこねくり回すために使いだしたawkやperl、unix環境。言ってしまえば、遊びでやってた当時の余録で、還暦すぎても小遣い稼ぎができるんだから、なにが役に立つのか立たないのかなんて、その時にはわからないもんだわな。
仙人の弟子の雑巾がけ庭掃除のネタは深いものがあるなあ(しみじみ)
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
GBLシーズン14で初のVETERAN到達

ポケモンGOの対人戦GOバトルリーグ。
今は3月2日からスタートしたシーズン14で、今日、初めてレート2500以上のVETERANというランクに到達した。これは素直に嬉しい。
シーズン1から14までずっとやってきていて、ランク的には初心者レベルのACEというランクが上限。その中で勝ち負け上下して遊んでいた。
ちなみに、ポケモンGOのランクというか称号は、各々レートが
ACE 2000〜2499
VETERAN 2500〜2749
EXPERT 2750〜2999
LEGEND 3000〜
となっている。
ガチ勢なんかと比べると、
テクニック的な部分がまったく追いついてない。
→技の回数を数えるとか、技を撃つ・交代するタイミングを考えるとか。
そもそも還暦過ぎて、集中力や体力も追いついてこない。
→一日フルセットやる気力体力がない。
この程度のプレイヤースキルでも初心者レベルとそのひとつ上のレベルぐらいには到達できるということ。
2016年、ポケモンGOリリース当時からほぼ6年、長くやってるんでポケモンの育成だけはそれなりにできてる。なので、わたしの場合、対人戦で遊べているのはポケモンたちのおかげだ。
言ってしまえば、腕はヘボでもポケモンが揃ってればそれなりに遊べるのが、ポケモンGOの対人戦。
ACEという初心者レベルでやってても飽きないし、あれこれ考えるのは楽しいもんだ。
ポケモンごとに種族値があり、タイプによる有利不利があり、それを3体選出してゲーム開始。
有利な局面に持ち込んで、3体で勝つための道筋を探すゲーム、といってもいいのかな。多少はアクションゲーム的な要素がある、かもしれないけど、たぶん、昔懐かしの大戦略や信長の野望なんかの戦略ゲームや、スコードリーダーなんかの戦術級ボードゲーム、あるいは詰将棋なんかが好きなひとならハマると思う。
そのためのポケモンの捕獲育成という、育成ゲーム的な側面もまた面白くて、ウォーキングのモチベーションもあがる。
てなことも含めて、ほんと飽きないよなあ(しみじみ)
上のレベルを目指して「頑張る」のは、ゲームで「遊ぶ」というのとは違う。ゲームとの関わりかたは人それぞれ。遊んで楽しめればそれでいいんじゃないかな。
ハイパーリーグというレギュレーションでの到達だった。
使ってたのはこのパーティ。
GOバトルリーグで遊んでいるひとならわかってもらえる、かな。
今のハイパーリーグでリザードンとかファイアローに焼かれまくって酷い目にあったので、とにかくこの2匹は絶対許さないパーティ構成。
MVPはこのポケモン。育成にずいぶん時間がかかった。デザイン(見た目)も込みで好きなポケモンの一匹。シャドーのもやのエフェクトに浮かぶ白銀の姿は知る限りトップ5にランクイン。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
余白の強さ

なんじゃそれ?なんだけど。
映画でも小説でもアニメでも、フィクションは受け取る側の妄想の入り込む余地があるほど強い、ということ。1から10まで全部説明、解説されてる、送りて側の意図が押し付けられるものだとまったくお話にならない領域というのがあると思う。
小説と比べてビジュアルや音響も伴う映画なんかは受け取る側の踏み込む、妄想する領域が狭くなる、てなことが言われていて、それが長所であったり短所であったりするのも、納得なんだけど。
ワタシ的にハマっていて、何度観ても個々いろんな状況を勝手に広げて涙腺を決壊させてるのが「告白」(True Confessions)という映画。
いちいち、そこわからんよ、というのがあって、トムとブレンダの関係やトムと弟及び家族の関係なんかの説明はばっさり削除されている。だけど、それを「匂わせる」セリフややりとりで「わかる」んで、その余白に想いを馳せて「泣ける」んだ。
映画の評価としても、デニーロとロバートデュバルが出てるのにその評価?お前らどこ観てんだよ、というのを胸倉掴んでも言いたいんだけど。それはまた別の話。
小説だと最近40年ぶりぐらいで読み返した田中光二の「異星の人」
これもまた読んで受け取るこちらの裁量が大きい物語で、勝手に膨らませていちいち、それこそ勝手に泣いてしまう小説。40年も前の小説で、40年経って改めて対面するわたしの状況があっても、そこに入り込む余地があるのが強い。
同人誌の二次創作の功罪?んなものに功罪なんてのはなくて。
好きな物語を膨らませて自分の物語として取り込むのは、たぶんみんなやっていること。やらざるを得ないことで、それがあるからこその人類という種、なんだろうとも思う。
とかなんとか。
わけのわからないことをなんか吐きちらかしてるのは。マジすべてのひとに「告白」ロバート デニーロ、デュバルを観てほしいだけ。
世の中のひとの評価軸として
「告白」を観た/観てない
は、ひとつの確実な指針としてある
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
Chromebookで電子書籍を読む

正規のChromebookはgoogle playからアプリをダウンロードして使うことができる。
デスクトップやノートパソコンでAndroidアプリが使えるということになる。
やりたいことは。
ASUSのChromebook CX1101で電子書籍を読む、というか表示確認をしたい。
今のところ、ChromebookというかChromeOSで制作した電子書籍を確認するためには、
・WINDOWSのノートパソコンを起動して
・電子書籍ファイルを共有フォルダに保存して
・WINDOWS版のKinoppyを立ち上げて読む
これだけっちゃこれだけなんだけど、この「これだけのために」が面倒くさい。
手元のChromebookでそのまま確認できればらくちん。
てことで、ASUSのChromebook CX1101でも電子書籍を読めるように電子書籍リーダーを探してみた。
google play storeで確認したところ。
kindleとkinoppyはChromebookに対応していない。
kindleについてはgoogle play storeではなくて、Amazon アプリストアから直接ダウンロードすれば使えるらしいけど、いくつか手順が必要でそこまでやる?
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2206/15/news181_2.html
↑chromebookにamazon アプリストアをインストールする方法
大日本印刷のhontoがChromebookでも使える
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.eps.ebook_app.android
問題なくgoogle play storeからインストールできた。
すでにhontoで購入済みの本も本棚に同期されていて、すんなり読める。
ローカルの電子書籍、epubファイルを読ませるには、リーダーごとに指定された保存フォルダにepubファイルを保存する必要がある。
Andoroidアプリのhontoの場合は
/storage/emulated/0/Android/data/jp.co.dnp.eps.ebook_app.android/files/epub/
↑ここにファイルを保存する。
chromebookではどこに保存するのか探してみた。
chromebookの「ファイル」アプリで「マイファイル」→「Playファイル」
「すべてのPlayフォルダを表示する」にチェックを入れると出てくる

/mnt/chromeos/PlayFiles/Android/data/jp.co.dnp.eps.ebook_app.android/files/epub/
↑ここにファイルを保存する。
とりあえずはこれでOKかな。
ほんとは本体に保存するのではなくて、作業しているSDカードをlinkしたいところだけど、
ln -s
で権限がないとはねられる。Playファイル以下にあるフォルダ側の権限の問題っぽい。
最終的に納品前にkindle previewerでの確認も必要なので、WINDOWSを立ち上げることになるんだけど、途中途中のちょっとした確認はこれで手間がずいぶん省ける。
電子書籍を自分が読む時はスマホなんだけどね。
昭和の書籍の文字サイズは老眼には厳しいんで、古本ではなくて、文字サイズを変更できる電子書籍がありがたいんだよなあ(ポンコツ)
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」