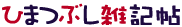colabで使うstablediffusionの小ネタ

google colabでstablediffusionを試していて気になったところの小ネタ。
…というか python は初めて。
・画像サイズがデフォルトだと512x512のスクエア
大昔ハッセルとかがスクエアフォーマットだった記憶もあり、これはこれで、好きなんだけど、たとえば、stablediffusionで電書の表紙なんかを作りたいとなった場合、スクエアだとよろしくない。縦長の画像が欲しい。
image = pipe(prompt, height=768, width=512)["sample"][0]
当てずっぽうでやってみたら、たまたま意図通りだった。イメージを作る呪文をパイプで渡すところに高さと横幅を指定してやればOK。ただ、512x1024でやってみたら OUT OF MEMORY でエラーになる。大きなサイズを扱いたければ有料のコースがあるよ、とお知らせ。無料で使わせてもらってるからしょうがない。
・画像ファイルを複数作りたい
一発で期待通りの画像が取り出せることはなく、ひとつのプロンプトで何回も取り出して、その中から選択、となる。一回ずつコマンドを叩くのは効率が悪いので、一回叩いて2つ画像を取り出すようにした。
import time
for i in range(2):
ut=int(time.time())
fname = str(ut) + '.png'
image = pipe(prompt, height=768, width=512)["sample"][0]
image.save(fname)
書き出すファイルは、ファイル名をタイムスタンプにして上書きしないように、ちょっと工夫。
range(2)、2回と言わずもっと回数を増やしてもいいんだけど、とりあえず様子見で。
縦長画像
beautiful concept art of KAWAII,
a girl walks on the street.she is seventeen,
steampunk city,AKIHABARA,
rim light,wide angle,sharp focus,
pixiv rankin,highly detailed,arknights,4K
KAWAIIやpixiv、arknightというキーワードはキャラがそれっぽくイマドキになる呪文。

ポートレイトの呪文も試してみた。
beautiful concept art of KAWAII,
portrait of a girl,full body,glossy eyes, blonde,
high contrast,rim light,sharp focus,
pixiv rankin,arknights,highly detailed,4K



blondeではなくblack hairも試したんだけど、噂通り、金髪の方が安定する。なんでや。
[2022/09/19 23:07:40] 追記。
今日時点、colabで使ってるコードをメモしておこう。
from diffusers import StableDiffusionPipeline
import matplotlib.pyplot as plt
import time
import random
import torch
from google.colab import drive
drive.mount('GoogleDriveのパス')
最初の2行はお約束。
import time
→ファイル名にタイムスタンプを使うのに必要
import random
→ランダムseed生成に必要
import touch
→seedをpipeに渡すために必要
import drive
→生成した画像をgoogle driveに保存するために必要
google driveのパスは「/content/gdrive」とか適当に。
上記、いろいろ必要なものをインポートしたら以下のコードが使える。
pmt_fname = str(int(time.time()))
with open('GoogleDriveのパス' + pmt_fname + '.txt', 'w') as f:
f.write(prompt)
for i in range(4):
seed=random.randrange(0,2147483647,1)
#seed=1349413827
gen=torch.Generator("cuda").manual_seed(seed)
#ut=int(time.time())
#fname = str(ut) + '-' + str(seed) + '.png'
fname = pmt_fname + '-' + str(seed) + '.png'
image = pipe(prompt, height=768, width=512, generator=gen,num_inference_steps=200)["sample"][0]
image.save('GoogleDriveのパス' + fname)
とりあえず、ひとつのプロンプトでタテ768pxヨコ512pxの画像を4枚作る。
ステップ数はデフォルトは50。多くするとそれだけ時間がかかるけど、細部まで作り込まれるということで200にしてみた。
ファイルはgoogle driveに保存される。
タイムスタンプ.txtという名前でプロンプトのテキストファイルを保存
ex.)1663466109.txt
プロンプトのタイムスタンプ+ランダムseed.pngという画像ファイルを生成保存
ex.)
1663466109-1096018807.png
1663466109-1253973203.png
出来上がった絵をみて、惜しいなあ、ここもうちょっと色味が地味なのがよかった、とか思った時に元になったプロンプトが残るので修正変更試行錯誤も簡単になる。そして何より、
StableDiffusionは、同じプロンプト、同じseedを渡すと、同じ画像が生成される。
これがキモというミソだろう。
構図はいいのに、なんでこんな格好してるんだ、とか、ここは空に月が欲しかった、てな時はseedを同じにしてプロンプトを少しいじると同じような構図で違う絵が出てくる。欲しい絵に近づけることが可能になる、かな。
検索するとAIがらみ、技術的な話にたどり着いてしまうんだけど、わたしのような素人はこんぐらいの理解で蛮勇するのでちょうどいい。
以下3枚は同じseedで生成
High quality concept art,
landscape of steampunk city with a monk,
riverside street,river babbling,
sunlight pouring down,
forest of skyscrapers,
a monk walks on the path,
rim light,wide angle,
sharp focus,highly detailed,
digital art illustration,
art station trending,playstation5,4

High quality concept art,
landscape of cyberpunk city with a monk,
TOKYO AKIHABARA,
riverside street,river babbling,
sunlight pouring down,
forest of skyscrapers,
a monk walks on the path,
rim light,wide angle,
sharp focus,highly detailed,
digital art illustration,
art station trending,playstation5,4

High quality concept art,
landscape of deep forest with a monk,
riverside and golden pond,
river babbling,
sunlight pouring down,
sunlight filtering through trees
a monk walks on the path,
rim light,wide angle,
sharp focus,highly detailed,
digital art illustration,
art station trending,playstation5,4
1枚めを最初に生成。
2枚め。スチームパンクじゃなくてサイバーパンクの街に、TOKYO、AKIHABARAも追加。
3枚め。街ではなくて森の中にしようと思ってプロンプト文字列の変更が大きかったようで、Seedの魔力もあまり効かなかった。
もうひとつ。
ネットだと画像の解像度は72dpiでも足りるんだけど、紙印刷だとカラーは最低300dpi、モノクロは600dpi必要となる。google colabで使うStableDiffusionの解像度は72dpi。設定で可能になるかもしれないけど、わからないんで、あれこれ検索。
同じくAIの技術を使って画像をリファクタリングする?アップコンバージョンするReal-ESRGANというのがあった。
これのおかげで512x768 72dpi程度で出力される画像を高精細化して300dpi、紙印刷にも耐える画像として使えるようなった。
変換前
変換後
なんか違いのわかりにくいビミョーな例になってるけど、輪郭あたりをみてもらえると一目瞭然。StableDiffusionとReal-ESRGANの組み合わせでまた可能性が広がる。
StableDiffusionでステップ数をあえて低くして作った画像を、Real-ESRGANで高精細化して細部を作り込むというやり方もできる、かも。
Real-ESRGANの公式ページ
https://github.com/xinntao/Real-ESRGAN
これもオススメ、ていうか必需品。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
StableDiffusionの呪文?

画像生成AIが面白くて、google colabでお試し中。
AIからどんな画像を取り出すのかは、AIに投げる言葉次第。呪文と言われるのもわかる。
↓こちらが丁寧で詳しいのでオススメ
魔術そして理解するお絵描きAI講座
https://note.com/fladdict/n/n0f0be20e3e23
ていうか、これは必読。
具体的な呪文の例はこちら
https://lexica.art/
検索窓にpixivとかplaystation5とか入れるとわかりやすい。
で、以下はド素人が多分に間違った知見を元に書いてるヨタ。
AIに投げる呪文はプロンプトと言われていてその構成は以下が最適
<全体のフォーマット><主題><主題の補足><作者><全体の補足><フレーバー>
「美術館のサイトなんかでどんなキャプションがついてそうか?」を考えて呪文を組み立てると良いらしい、AIに意図が伝わりやすいとのこと。
Buddha walk on the surface of the moon
呪文はこれだけ。前記した構成でいうと「仏陀が月の表面を歩く」主題だけ。これはこれでAIまかせで面白い。
ただ、ほかのひとの上げている画像と見比べてみて、画質というか描画が全然ダメだなあ、と。ほかのひとの呪文を覗いてあれこれつけ足してみたら安定した、かな。
High quality concept art,
Buddha walking on the surface of the moon,
high contrast,
sharp focus,
art station trending,
highly detailed,
digital painting,
digital art,
4k
「主題」は最初と同じ
Buddha walk on the surface of the moon
で、それ以外にいろいろ見様見真似、それこそ呪文状態で付け足した。
「全体のフォーマット」に High quality concept art
を指定。
コンセプトアートはいい感じの絵ということ、でいいかな。ここは他に油絵とか水彩画とかを指定するといいらしい。
「主題の補足」にコントラストが強くてピントぴったりという補足説明。
「作者」は「art stationというゲーム紹介サイトのトレンドにありそうな」ということにした。ほかにpixiv rankinだと「ピクシブでランクインしてそうな」という使い方。ここにゴッホとかレンブラント、京都アニメーションやジブリなんかも。
「フレーバー」として細部まで細かい、デジタルで描かれている、画質4K。
このフレーバーに、カメラのレンズや開放値、シャッタースピードなんかを入れるのも効果的というのが、ネットで学習するAIならでは、というやつだろう。
美術などを学問的系統的に学ぶのではなくて、ECサイトのカメラ販売ページなんかにある作例を脈絡なく取り込んでるのでこちらの側からアクセスも面白いということになった、んだろなあ。
たぶん、以下からフレーバーに「playstation5」とか「unreal engine」とかつけた。ゲーム画面を指定したらそれっぽいものが出るようになった。安定した、かな。
月の上ばかりじゃなく、サイバーパンクの街にしてみたり

日本の寺にしてみたり
スチームパンクにしてみたり
坊主が歩いてばかりなので跪いてお祈りするようにしてみたり

坊主ばかりじゃなくて女の子にしてみたり
スチームパンクな街に秋葉原を指定してみたり
こりゃキリがなくて面白すぎる。
意図した絵を作るために呪文の精度を上げれば仕事に使えるし、意図しない絵が出てきたらそれを元にストーリーを作る・大喜利を始めるのも面白いし。
ちなみに、権利的には商利用も自由。本、同人誌の表紙や挿絵が欲しいけど、絵が描けないとか頼めるひとを探すのが難しいというような場合、この画像生成AIの出番。
ただし、実在の人物なんかを呪文のタネに仕込んだ場合、肖像権にブチ当たって弁護士と内容証明が飛んでくる可能性が十分あるので、そこだけ注意。
まだまだ遊べるなあ。
[2022/08/30 10:24:41]追記
今日時点で。呪文のテンプレは以下
High quality concept art,
「ここに具体的な描写内容を英語で記述」
rim light,
wide angle,
sharp focus,
high contrast,
highly detailed,
digital art illustration,
art station trending,
playstation5,
4K
なんとなく、だけど。StableDiffusionは縦長の構図は苦手かなあ。
あとは出てきた絵をネタにしたエントリを頑張る
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
AIでテキストから画像を生成

いま話題の画像生成AI「Stable diffusion」を使ってみた。
ローカルにダウロードしてPython環境、Anacondaとかを作ったりGitからStable Diffusionのソースコードを持ってくるのは大変なので、とりあえず、googleのcolabで使ってみた。
ほんとだったら、ローカルに構築するのがいいんだけど。
とりあえずアカウントが2つ必要。
・googleのアカウント
→gmailのアカウントで、ほとんどの人はすでに持ってるのでは?
・huggingfaceのアカウント
→これは持ってるひとが少ないと思うけど、簡単に作れる。
https://huggingface.co/settings/profile
わたしのようなド素人のヨタじゃなくて、以下のサイトがオススメ。
Google Colab で はじめる Stable Diffusion v1.4
https://note.com/npaka/n/ndd549d2ce556
[Stable Diffusion] AIでテキストから画像を生成する[Python]
https://www.12-technology.com/2022/08/stable-diffusion-aipython.html
とはいえ、自分メモ。
・huggingfaceでの作業
huggingfaceのアカウントを作ったらhuggingfaceのプロフィールページの左メニューからアクセストークン(ACCESS TOKEN)をクリックしてアクセストークンのページを開いてひとつ新規に生成して取得する。
権限にreadとwriteがあるけど、readで大丈夫だった。
・google colabでの作業
https://colab.research.google.com/?hl=ja
↑ここにアクセスしたらまずは下準備
「ノートブックを新規作成」
素っ気ないページになる。これ、古のターミナルみたいだな。
てのはともかく、やることは以下の4ステップだけ。
1)
「編集」→「ノートブックの設定」→「ハードウェアアクセラレータ」を「GPU」に設定。
2)
次にこの▶のところに以下のコマンドを入力。
!pip install diffusers==0.2.4 transformers scipy ftfy
▶をクリックするとコマンドが実行される。
3)
インストールが済んだら、「+コード」をクリック。
次のコマンドを入力欄を追加してライブラリのインポート…これをしないと、次のフェーズで403エラーになって止まってしまった。
from diffusers import StableDiffusionPipeline
import matplotlib.pyplot as plt
4)
そして以下で準備完了となる。
TOKEN="Huggingfaceで取得したトークンをコピペ"
from diffusers import StableDiffusionPipeline
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained("CompVis/stable-diffusion-v1-4", use_auth_token=TOKEN)
pipe.to("cuda")
準備が済んだらいよいよ画像を生成だ。
▶のところに
prompt = "Japanese Bobtail Cat on the Moon" #@param {type:"string"}
image = pipe(prompt)["sample"][0]
image.save("test01.png")
とやってできたのがこの画像
promptがキモ。ていうかAIにどんな画像を作らせるのかAIと話し合いになる。
今回は最初だし「Japanese Bobtail Cat on the Moon」とやってみたけど、そんなに面白い画像がすぐに出てくるわけでもなく、これにしても4回目ぐらい、だったかな。
デフォルト状態で1枚生成するのに20秒ほどだった。
「AIと話し合い」と書いたのはこのリクエストがすべてで、どんな画像を出せるかは話し合い次第。プロンプトをリクエストするひとの腕次第という意味もある。たぶんこの分野、こんな画像が欲しい、というのを翻案して噛み砕いてAIのわかる言葉で伝えるニーズがあるだろうな。
創造とか創作というのは人間や神様だけのものという聖域感がある。
だけど、神様については知らないけど、人間の創造もまったくゼロからというものではなく、いろんなもののインプットの坩堝があって初めてアウトプットが出てくる。
てことはこのAIもやってることは同じ、大量のデータをインプットされて学習したモデルから適当と思しきものを引っ張り出してそれらで合成して作り上げてアウトプットとする。
一部界隈が騒がしいのもわかる気がする。
ほんと、これはひととAIの棲み分け、区別というか、倫理の話にもなりそうだし、SFのネタが現実になりそう。
ちなみに生成した画像は権利関係的にはフリーなので(著作人格権とか肖像権にぶち当たることもありそうだけど)商用利用もOKとのこと。
とりあえずgoogleで使ってみたけど、いろんなパラメータをいじれるはずなのでローカルで構築してみたいとこだなあ…て、今うちで使ってるパソはグラフィックが弱いからパソコン買い替えになるだろうし、当分無理、か。ビンボはつらいぜ、ちくしょう。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
WORDの小ネタ

ワード(MS WORD 2010)についての小ネタ
毎度毎度検索して探すのも面倒なので、ここにメモ。
傍点(圏点)のついた箇所を検索
・「ホーム」→「検索」
・検索窓の右にある小さな▼をクリック
・「高度な検索」→「書式」→「フォント」
・「すべての文字列」の項目にある「傍点」を選択(ゴマ)して「OK」
・ひとつ戻ったところで検索窓を空欄にして「次を検索」
「書式」の先の「フォント」から設定する…て、気づかないだろ
ルビを検索
・「Alt+F9」を押して「ルビをフィールドコードで表示させる」
・検索窓の右にある小さな▼をクリック
・「高度な検索」→「オプション」
・「あいまい検索」のチェックを外す
・「特殊文字」→「フィールド」
・検索文字に「^dEQ」を入力(「^d」はデフォルトで入っている)
・「検索する場所」を「メイン文書」にする
ルビの数をかぞえるだけなら置換に適当な文字を入れて実行。置換された数が出るので確認できる。
↓以下のサイトを参考にさせていただきました。多謝!
小ネタ集 - 成城大学文芸部 萬屋夢幻堂
Word2010-2016: ルビの検索(一括書式変更など) - 教えて!HELPDESK 
オフィスソフトについて検索してるといろんなTipsが掲載されていて助かるんだけど。
んなTipsが必要とされるってだけでオフィスソフトはクソだ。
デフォルトがほんと余計なお世話だらけでかえって使い勝手を悪くしてるだろ。うんざり。
ワード、エクセルは滅んでくれろ。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
winmergeという神ツール

バージョン管理ツールというのがある。
バージョン管理ツールというのは「テキスト」の変更履歴を管理するツールのこと。
今日時点だとネットではgitが決定版と言われていて、ほかにもCVSやsvnなんてのもある。
このあたりは、ひとつのプロジェクトをチームで動かしているようなケースでは必須のツールだろう。実際にFreeBSDやlinuxなどOSのソースコードはこの手のツールで管理運用されている。
ただ、個人で、ひとりの作業で使うにはどうだろう。
これからはgitだ、というんでインストールしてみたものの、個人でちまちまやってる分には大袈裟すぎて管理のための管理作業が発生して面倒なだけだった。仕事で他の人が管理しているツリーにメンバーとして参加、コミットしたりとか程度でがっつり使ったこともないし、実際のところはよくわかってない。
とはいえ、
「納品20210110.zip」
「納品20210110b.zip」
「納品20210110-修正1.zip」
「納品20210110-修正0115.zip」
ということもよくあって、変更履歴の管理はさすがに痛感しているので、納品後の修正や差し戻しがあったら(って、なんでやねん、という話だけど)ディレクトリごと別ディレクトリとしてコピーして作業するようにしている。
こういう時に、もう10年ぐらい重宝しているのが、winmergeという差分確認、マージ(差分擦り合せ)のためのツールだ。
https://winmerge.org/
これがなければ仕事にならないし、これのためにWINDOWSを使い続けている、といっても言いすぎじゃない。
神ツールとはまさにwinmergeのことを言う。
2つのファイルの差分をチェック
百聞は一見に如かず。
ふたつのファイルで違いのある箇所が左側のルーラーの黄色の部分。
メインの左右画面では違いのある箇所が赤く表示される。
差分、変更箇所がすぐに目視できる。差分のある箇所を個別にどちらかに合わせることもこの画面ですぐ、だ。編集されて上書き保存されたら元ファイルは拡張子が.bakになって保存される。
これはeasy_epubという電子書籍作成スクリプトのソースコード。
左側がオリジナルのリフローEPUB用、右側がハイブリッド対応版
無駄に機能追加したり、つぶしきれないバグフィックスをするたびに、別フォルダにコピーして修正。修正したらwinmergeで修正箇所、修正漏れの確認をして動作確認。動作が意図どおりじゃない時などもwinmergeのおかげで修正箇所の洗い出しが一発なので楽チン。
ディレクトリごとの比較
winmergeにファイルではなくてディレクトリを指定して読みこませると、ディレクトリ内で違いのあるファイルがこれまた一目瞭然。
違いのあるファイルが黄色くハイライトされている。
これはdoncha.netのサイトの一部。スクリプトやhtml、css、javascriptなどいろんなファイルがてんこ盛り。
webの場合、デザイン変更ひとつ取ってもhtml、構造の変更なのか、css、見た目のデザイン変更なのか、そのためにスクリプトやデータベースの変更は必要なのか、などなど、いろいろ絡んでくる。どのファイルを変更しなきゃいけないのか、実際どのファイルを変更したのか。
winmergeが一目で教えてくれる。
差分のあるファイルを選んでクリックすると2つのファイル比較となり編集更新ができる。
テキストの変更箇所、差分を教えてくれる、直感的で超絶便利なツールがこのwinmergeだ。
ということは。
プログラムとかエンジニアだけのものじゃなく、webのソースとかデザイナーだけのものじゃなく、テキストを扱うすべてのひとにとっての神ツールということだ。
小説書き、モノ書きのひとにとっても、語尾や用語を合わせる前後や、追加エピソードやセリフの確認とその比較に使える。
一太郎やワードはさらにモノ書きに特化した機能満載だから、それで間に合っているかもしれないけど、一太郎もワードも入っていないパソコンもあるしね。
gitやsvnのように更新、変更履歴を追うことはできないけど、winmergeさえあれば、個人でやる仕事については、万全磐石の安心感。
だがしかし、めちゃくちゃ残念なことにwinmergeはWINDOWS版しかない。macにもchromebookにも当然ない。
わたしの弁当箱macはすでに最新のOSアプデ対象外となっていて、今はただの鉄の箱だからいいとしても、去年末あたりから使い始めたchromebookで使えないのは致命的。このchromebook化したASUSのvivobookで委託のWEB運用、請負の電子書籍制作をやっていて、特に電子書籍の方はwinmergeでの作業がはいる。
原本、底本の元データと電子書籍化したEpubデータの差分チェックは欠かせない。
作成中にルビを取りこぼしたり、全角の空白を潰したりしてしまうこともあるし、修正依頼に対応したら修正の必要がない箇所に影響したり、などなど確認項目は多岐に渡る。
そのためだけに、WINDWOS機を起動してwinmergeで確認してたんだけど、さすがにどうにかせんといかんなあ、と必死のぱっちでぐーぐる先生。
「漢」ならdiffで頑張れ
とか言われてるんだけど、いくらなんでも無茶すぎ。そこでvimの出番となった。
エディタのvimがほぼ万能で、こいつもできないことを探すほうが難しいやつ。
vimdiffという差分チェックができるモード(?)がある。見た目もwinmergeとほぼ同じ、ていうか、vimdiffの方が先だろう。これで、ディレクトリ内のファイルの比較もできればなあ、と。
たぶん、いや、間違いなくvimだけでできると思うんだけど、わたしにそんなスキルも時間もないので、diffでディレクトリ比較した結果を適当に整形して読みこんで画面分割してやってみることにした。
winmergeほど便利じゃないんだけど、やりたいことはほぼこれでできることとなった。
ちなみにvimについては
https://knowledge.sakura.ad.jp/23018/
↑こちらのサイトがおすすめ。
しかしなあ。
21世紀にもなって、ラクをしようとするな、ツールなんか信用するな、というクズな仕事場もあって心の底から呆れるばかり。どうぞそのまま滅んでくださいとしか。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
22980円のノートパソコンvivobook購入


急遽必要に迫られて買ったASUSのノートパソコンVivobook。
サイバーマンデーもあって、22980円という噓みたいな値段でびっくり。
Windows10HOMEのノートパソコンが今時のスマホより安いのだ。
通常の32800円でも十分安過ぎる。
サイバーマンデーでさらに安くなって22980円のノートパソコンだ。
型番W203M
CPU Celeron N4000 1.10GHz
メモリ 4G
HDD 32G
OS WINDOWS10(64bit)HOME Sモード
ディスプレイ 11.6インチ
解像度 1366x768
バッテリ 最長15時間
アマゾンの詳細ページ→ https://amzn.to/2EtkRHZ
注意するところが2つ。
その1
載ってるOS、WINDOWS10HOMEの「Sモード」というやつ
このままだとWINDOWS STOREからしかアプリをインストールできない。WINDOWS STOREにないアプリは使えないということ。
解除は簡単だった、ような気がする。
アプリをインストールしようとしたら、Sモードを解除しますか?てなダイアログが表示されたのでそこでWINDOWS STOREのアップグレードをしたらSモードが解除された、と思う。
…というのも、別の要因でWINDOWS10を設定からクリーンインストールしなおしたので、その結果Sモードじゃなくなった、のかもしれない。
ごたくはともかく、
Sモードのままでは使いものにならないので解除必須。
その2
スペックを見てわかる通り、HDD(ストレージ)が32Gしかない。
これじゃ今時フツーにギガ単位で容量を使うアプリをインストールしてしまうと、あっという間にHDDがいっぱいになってしまって、WINDOWSのアップデートすらできなくなってしまう。
そこで、やっぱり急遽秋葉原に行ってマイクロSDカード128Gを購入(3750円也)
その一部を仮想ディスクにして、アプリはそこにインストール。また、各種データもSDカードに保存するように設定した。
WINDOWS10では、そのためのソフトを別途用意することなく、デフォルトで仮想ディスク機能があったので助かった。
「ディスクの管理」からSDカードに仮想ディスクを設定する。
仮想ディスクはファイルシステムをNTFSで設定する必要があった。それに気づかず、exFATでフォーマットしてしまったのでやり直しその1。
仮想ディスクの作成は時間がかかることに気づかず、仮想ディスクを作成中だというのに別操作をしてしまったりSDカードを抜き差ししてしまったりしたのでやり直しその2。
特にその2が致命的で、うまく認識してくれなくなったので、上記したWINDOWSのクリーンインストールからやり直すハメになってしまった。
無事、仮想ディスクが作成・認識できて必要と思われるアプリをインストールしてしばらく使った状態のストレージ状況が以下。Cドライブの残りが7G程度。仮想ディスクにインストールしてなきゃパンクしていた。
また、デフォルトの保存先などをCドライブ以外、SDカードに設定できるので、アプリのインストール先やデータ保存先をすべてSDカードに設定した。
てことで、格安ノートパソコンVivobookにSDカード(仮想ディスク)は必須。
使い勝手だけど。
これがもう3万円しないノートパソコンとは思えないサクサク感。快適のひと言。
64ビット版だし、メモリも4G載ってるからだろうか。グラフィックもたぶん問題ない。
アドビのフォトショップとイラストレーター(無償版)もレスポンスに問題なく使える。
エクセル、ワードも同じく今まで通り普通に使える。
エディタ(vim)もperlも、epubcheckのためのjavaも普通に使えて、電子書籍制作環境のできあがりとなった。
kindleも紀伊國屋kinoppyもサクサク動作する。
キーボートのキー間隔やキータッチもミスタッチすることなく使えるレベルで見た目以上に良い感触だ。タッチパッドはもともと苦手なのでマウスを利用している。
1kgを切っていて軽くて薄くて、持ち運びも楽勝。
…ただ、樹脂製というか大阪でいうところのいかにも「プラッチック」なので、耐久性には期待できないかな。
でも、この値段でこの性能、感触だ。壊れた時のためにもう2台ぐらい確保しておいてもいいと思う。ASUSはすげー。
ていうか、こいつはほんと全力おススメできる。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」