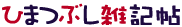- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 100円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 300円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 400円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 490円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 600円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円
doncha.net制作・発行:KindleやiBooks、楽天kobo、BOOK☆WALKERで読む電子書籍
電子書籍

電子書籍だ、と沸き立っていても、わたし自身、ソーシャルだとかコンテキストだ、なんて、まるで興味がない。てこというと本質がわかってない、と叱られそうだけど。
興味があるのはamazon。
誰でもamazonの販売網に作品を乗せることができる、てのが大事(だいじでおおごと)じゃないか。
営業的に、名前のない新人とか一作コケた作家は部数が取れず、出版すらできない。これでどれだけ可能性をつぶしてることやら。営業が欲しいのは村上春樹とか伊坂幸太郎とか東野圭吾。んなもん、営業職じゃない素人でも部数が取れるし売れる。名前のない新人作家、このひとをなんとか「売りたい」「みんなに知ってもらいたい」という意識、というか余裕がないんだよねえ。
てことで、amazonなのだ。
なんでもありで玉石混淆状況となったら、やっぱり聞いたことのない作家は誰も見向きもしないよ、という話ももっともだけど、本を出すことすらできないよりよっぽどマシ。個人で宣伝PRして少しずつ、身の回りから始めればいいのだ。そもそも、そのための道具としてネットがある。
出版社にしても部数縛りがなくなれば今よりもっと余裕がでるはず。大手版元が編集して仕掛けてる、というブランド力とか信用は健在なので、電子書籍になっても出版社の役割はなくならない。
てなことをぼーっと、青空キンドルを眺めつつ。IPAフォント、というか、kindleだと少し太めのフォントがいいのかなぁ。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」