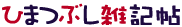- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 400円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 300円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 600円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円
doncha.net制作・発行:KindleやiBooks、楽天kobo、BOOK☆WALKERで読む電子書籍
電子書籍無料キャンペーンの効能

電子書籍の価格設定は悩ましい、というネタで以前書いた。無料キャンペーンをするのは「作者作品を知ってもらうため」
『KDPの価格設定、バーゲン?』https://t2aki.doncha.net/?id=1359633724
「本を売るために」なにがしか無料キャンペーンの効能はきっとあるんだろう。データを見ればきっと有料購入に繋がることもあるんだろうとは思う(実際ウチの場合も、無料を読んで面白かったからと、有料本も買ってくれたかたがいらっしゃる)
それでもあまり積極的になれない。
ネットを見ると(自分の観測範囲)
相変わらず「ネットはタダ」と思ってるユーザーが大半のように見える。
目先の客(UUだのPVだの)が欲しくてタダでコンテンツをバラまくWEBベンチャーが多いように見える。
曰く。収益は広告モデルなので、ユーザーさんには課金しません。
きっと当初は理想もあったんだろう。でも実際のところはどうなんだろう。
広告収入のためにエサとしてコンテンツを集める。広告収入がいくらになるかわからないし、エサに金などかけたくない。ましてやエサ=コンテンツに対する敬意などどこにもない。
広告収入のためにエサとしてユーザーを集める。タダのコンテンツで集まってくるんだからテキトーなものを放り込んでおけばいい。集めさえすれば広告収入となる。
広告に金を出す企業側。まだまだ不景気だ、実際に金を掴んでこない広告費なんて少しでも削って営業部隊に金を回そう。
かくして、ネットは金にならない・金にするのが難しい(最近のカタカナ言葉でいうと「マネタイズが難しい」)となる。収益は広告モデルです、なんて言ってるうちにモノがどんどん劣化していく。
気がつけば、夢のWIN・WINがLOSE・LOSEみんな負け状態になりかねない。
ようやく立ち上がってきた電子書籍は、読者が本を直接買う(買うと書くとDRMうんぬんとツッコミが入るけど、いちいち面倒なのでここでは「買う」)
ビジネスモデルなどと小難しい言葉の入る余地なく、気に入ったものに・好きなものに、お金を払う。昭和の昔から変わりなく当たり前にあるシンプルな世界。
電子書籍というパッケージの登場で、やっとネットでコンテンツに対価を支払う、という空気が醸成されつつある。なので、無料本・無料キャンペーンは慎重に様子をみながらやろうと思う。
前方に広がる焼け野原を繰り返したくないよなあ。
[12/08 21:25:07]追記。
当面、無料キャンペーンはやらない。
iBookstore、 google playで無料頒布が可能。有料のタイトルを無料キャンペーンにするのではなくて、告知用に最初から無料本を用意して、iBookstore、google playを利用する。
↓こちら
『ibooks と googleブックスの無料頒布作品』
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」