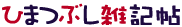電子書籍の中抜き

噂話のヨタ話。データも根拠もない伝聞と思いつきの垂れ流しなのであしからず。(ネタ元は、中小零細版元、電子書籍専門の零細版元、電子書籍も始めた零細版元、フリーのライター、デザイナーとの雑談。印刷会社系・ネットベンチャー系の電子書籍取次ぎ主催交流会噂話の又聞きとか)
電子書籍オリジナルで商売をしている中小零細版元の売上は好転することなく厳しい状態が続いているらしい。業務縮小や人員削減なんて陰気な話がひそひそと。
・大手版元の本格参入で先行者利益(先発優位)が吹っ飛んだ。
・低価格帯はそれこそアプリと同じ競争激化、有象無象に埋もれてしまった。
・同じランキングでも、去年暮れから今年頭までと、今年の春以降ではダウンロード数(購入数)がまるで違って激減した。
上記の雑談は、
・紙の資産がある・ブランド力のある大手既存版元はやはり強いということ。
・コンテンツ制作にあたって、実売だけだと金が回らないということ。
この2点ということか。
電子書籍商売は難しいんだなあ、というのは以前にもヨタ話を。
『電子書籍は版元には厳しいらしい』 (2013/4/28)
中小で少人数とはいえ、事務所の家賃光熱費、人件費もろもろの固定費を考えると、定価99円とか190円、290円の本を最低でも何冊売らなきゃいけないのか、だ。
紙印刷のベストセラーだと1タイトルで、ン10万部なんて部数が出るけど、電子書籍のダウンロード数ってどうなんだろう(検索すると https://bestseller.digital-dokusho.jp/digital/index.html 10万部以上というケースもあるのか)そのベストセラーを出すまで辛抱がきくか・体力があるかどうか。
電子書籍で、取次ぎや出版社を「中抜き」ということが話題になったけど、別の意味の中抜き現象かもしれない。
現状うまく転がりそうなのは、紙資産のある既存版元か、売上が死活問題にならない個人レベル。この二極化で中抜きされるのは電子書籍専門の中小零細企業ということだったか。
(この手の、市場がどーした売上がどーたら、という話題に過剰反応するのはネット屋ばかりに見えるのは、危機感を募らせてるからかなあ、と邪推)
だらだら、つらつら書いてみたけど。
「中抜き」って市場が確立されてから出る言葉。その市場は去年暮れにやっと立ち上がったばかりで、まだ1年もたっていない。現状トップのKindleストアの売上がどのぐらい伸びるかで市場のいろいろが決まってくるんだろうなぁ。
ネットのスピード感とかだと、もう10ヶ月。でも、まだ10ヶ月。
我が家は地道に続けて行こう。
[08/08 20:05:43] 追記。
電子書籍で金になりそう・ひと儲けなどと、参入してきた安直なハイエナ系のネット企業は退場いただく。ということでいえば、わりと正しい淘汰のプロセスに入ったのかな、とも言える、かも。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
リフロー縦書きのセンタリング小ネタ

EPUB3リフローの縦書きで困るのが、縦書きの中でのセンタリング。
縦書きで中央揃えといったら、ページの左右に対して中央に配置されることだろう。なのにページの天地に対して中央揃えされてしまう。なんじゃらほい。
タイトルが1〜2行だけあるような扉ページに関しては以前書いた通り
『EPUB3リフローレイアウトで扉ページ』 (2013/4/1)
bodyを横書きにして、タイトルの入るブロック要素をセンタリングして、ブロック要素の中を縦書きにすることで解決。
・EPUBcheckではエラー、警告ともになく通る。
・リーダーは、ibooks kindle koboがOK。KinoppyがNG。
小見出しなどにも縦書きのセンタリングを使いたいことがある。
この小見出しは、数字部分と下の小見出し2行の部分で構成。
【タイトルや小見出しの仕込みが以下】
・opfファイルのmanifestとspine部分。タイトルと本文の2つのファイル構成
・タイトルページのxhtml
・本文のxhtml(小見出しのある冒頭部分)
この小見出しのセンタリングがうまくいかずに試行錯誤。line-height で調整できることに気づいた(って、WEBでは行の高さを揃えるのに使われる常套手段。とっとと気づくべきだった)
文字の大きさは、数字部分が2em。文章部分が1em。
左から
1)
数字はline-heightの指定無し(bodyに指定されたline-height:1.7)
文章はline-height:1
2)
数字のline-height:1
文章のline-height:1
3)
数字のline-height:1
文章のline-height:1.5
3)
数字のline-height:1.4
文章のline-height:1.5
文字の大きさに応じてline-heightは違ってくる。計算で出るけど計算するより身体で覚える現物合わせ。
あっさりさくっと、縦書きの時は text-align:center が左右に対してセンタリングしてくれればこんな面倒なことをする必要はないんだけどね。
[08/07 20:56:59] 追記。
上記の小見出しは、文字サイズを大きくして縦におさまらなくなると、数字部分と文字部分が横並びに。floatで並べただけのブロック、というので同じ。リフローは面倒くさいことが多いなぁ。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
サンプルの縦書き表示

 この雑記帖を「縦書き」で検索するとしこたまヒットする。小説などの文章は縦書きであるべきだと思っている。根拠はない。
この雑記帖を「縦書き」で検索するとしこたまヒットする。小説などの文章は縦書きであるべきだと思っている。根拠はない。
EPUB3だ電子書籍だとここで騒ぎ出したのも縦書きができるようになったから。
この雑記帖で日野裕太郎作品のサンプルを立ち読みしてもらうのも縦書きでなきゃ意味がない。 「創作文芸見本誌会場HappyReading」 の立ち読みテキストも(無理やりではなくて、素直な)縦書きで表示したい。
てことで調べてるんだけど、FireFoxがいまだに対応していない。
困ったことに、FireFoxはサイトをコーディングしていくときに便利なアドオンがあって手放せない。
しかたがないので、この雑記帖では、現状はUserAgentで判定してSafari、Chrome、IEの時だけサンプルを表示するようにした。
https://t2aki.doncha.net/?id=1362724515
スクリーンショットは向かって左からIE、Chrome、Safari(WIN7)
この時、気に入らなかったのが、
・縦書きは右から左へ文章が流れる。
・ブロックに収まりきらない分は、左側にあふれる。
・スクロール指定をしたら、ブロックの下にスクロールバーが出て、右から左へスクロールとなる。
全然イケてない。
・ブラウザのスクロールは縦方向でそこに横方向ってどうなの。
・クリックなどのユーザーアクションを求めるのはかなりハードルが高い。
という理由もあるけど。そもそも…
本の段組みのように配置されて、右から左に読んだら、左下から一段下の右上に目線を移動するのが本当だろう。
ブラウザも目線も上から下。クリックなしに文章を追ってもらえる。
ということで、雑記帖でのサンプル縦書き表示は、文字数をカウントして一行ずつ、pタグで囲って「段組み」に流し込むこととなった。
禁則処理のレアケースでバグがあるけど勘弁してもらおう(自分に)
縦書き部分のCSS
ついさっきまでIEもダメだと思ってたのは内緒。
このIE用の指定を見つけたので、何度も似たようなことを書いてるのに、またこんな記事にしたというのがことの真相。
やっぱ縦書きにはこだわりたいんだよなあ
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
ひとくくりにしないでくれ

クラスタというのか、ちょっと前はレイヤーとかセグメントとか言ってたような気がする。属性とかカテゴライズとかの話題は賑やかだ。昭和の昔から団塊の世代vsシラケ世代など世代でくくるのは定番だし、血液型や星座も同じようなもんだろう。
ブログでもtwitterなどのSNSでも、属性でくくって一般化・概念化して、事件やひとについての論考…というか、溢れかえるしたり顔の数々。
エロ本出版社の頃ずいぶん痛い目にあった。
宮崎事件というのがあった。テレビや新聞、雑誌が連日報道、編集部にアポもなく時間関係なく押しかけてくる(最近知った言葉でいうとメディアスクラムとかいうらしい)
ロリコンのひとくくりに敷衍され、本が出せなくなりほぼ1年干上がった。
どうしてこんな事件が起こったのか、なぜ彼はこんなことをしたのか、わからないと不安なので、理由をさがす。それはいいんだけど、彼個人の問題じゃなかったか。「ロリコン」というひとくくりでいいのか。
てなことで憤慨したものだ。
当時、マンガ家たちと、何か事件があるたびに「お願いですから、この犯人の部屋から、妙な雑誌、コミックスが出てきませんように」
属性でくくって遊ぶのは面白いので自分もネタでやるけど、危ないと思う。
群れ・村に不安なことがあって、理解できないと、ねつ造してでも原因を作って安心したいというのがあるらしい。原因としてひとくくりにされた側はたまったもんじゃない。
人間は群れ・村社会に生きるので、必ず何かに属することになる。この手のことは本屋さんにいって、「社会学」「民俗学」「文化人類学」などと書かれた棚の前にいって、適当に本を引っ張り出して読めば必ず書いてあること。
よく言われるように、ロバート・B・パーカーの小説はマッチョな俗物だと思う。
『約束の地』
一般論はやめてくれ。それが、女性全員の問題なのか、ある特定の女の問題であるのか、おれは知らない。ただ、おれにわかっているのは、それが、きみの悩みの種の一つであるかもしれない、ということだ。そうであれば、解決できる。なにかを知っている、ということと、なにかを感じてそのように行動する、つまり、そうと信じることとは、別問題なんだ
『レイチェル・ウォレスを捜せ』
「おまえたち、だと?」私が言った。「おれたち?おれは、おれとおまえのことについて話してるんだ。おれたちやおまえたちについて話そうとしているんじゃない」
個別の問題を、一般化・概念化せず、一対一で向き合うところが「マッチョ」で「かっちょええ」んだ。
[07/29 10:51:16]
↑現実に起こりうる。シャレになってないよなあ。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
最近ネタもなく

去年秋から始まった一連の電子書籍制作ネタ事務手続きネタ、ストアネタなどわたしのところでは落ち着いた感じ。
(google play booksの管理ページ(個人出版でも使うページ)が7月中に劇的に使いやすくなるという噂を聞いたけど、その後音沙汰がない。どうなってんだろう)
小ネタばかり。
W8BENが受理されて課税(源泉徴収)が0%になっていたというのに、6月に30%課税された件は、何度もメールのやりとりしているけど、解決に時間がかかっていてすみません、ということで未解決。まだ時間がかかりそうで、気長に待つしかないな。
ウルティマオンライン(UO)が日本でオープンした当初Asukaサーバーで遊んでたんだけど、しょっちゅうサーバーダウンでプレイ時間が巻戻り。せっかく手に入れたアイテム、経験値がなくなって…「あなたの忍耐に感謝します」という素っ気ない画面を呆然と眺める。うおおおザッツアメリカ、というのを思い出した。
iOSデベロッパセンターがダウンしていた。一週間…豪快な落ち方だよなあ。
iTunes connectは年末年始の休みメンテも一週間近くとりやがる。いや、バカンスでお休みになられる。こいつもザッツアメリカな話だ。
EPUBを作成、kindlegenでmobiに変換して確認。というごくごく当たり前の作業。
・USB経由で、KindlePaperwhite、Fireの2台に流し込んで表示確認。
・kindlepreviewerで表示確認。
今までこの2パターンでやってたんだけど、クライアントからクレーム。ゴチックの表示指定なのにゴチックになってない、明朝じゃないか、何度言ったら直るんだどうなってんだ、と。
いや、スタイルシートで該当部分は何度見てもsans-serif(ゴチック)だし、ゴチックになっているのを確認してから先方に送っている。
結論:Send-to-kindleで送ったものを確認したところ、先方のいうとおり、ゴチックになってない。htmlやbodyにデフォルトのつもりで指定しておいたserif(明朝)がすべての要素に上書きされている、っぽい。
USB経由、kindlepreviewerと、Send-to-kindleでは解釈が違っていた、というオチ。
って、これにiOSも絡むんで、事前の検証はひたすら徒労感たっぷりの手間仕事だ。
さらに。
EPUBcheckでエラーも警告もなくValidでもストアごとのレギュレーションが違っていて、kindleだと問題なかったものが(mobiに変換する時によきにはからってるんだと思う)、ibooksだと通らずエラーになったりするケースも。
(引っかかりやすかったのが画像のサイズで、縦横かけて20万を超える大きさのものはibooksでは弾かれてしまう)
て、もう7月も終わりか。
この週末はもう8月。地元の夏祭り納涼祭り。わたしはことし順番で当番の班長なので、コキ使われることになっている。とほほ。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
結論はないまま現時点の整理

スクリプト記事、ノウハウ系の記事や市場についての記事と同じぐらいアクセスされるのが電子書籍のプロモーションというか売り方系の記事。そこには、無料キャンペーンどうなの?バーゲン価格にするとどうなの?という記事なども。
今、わたしがウチの電子書籍の値段を決めているのは、基本的に今年冒頭に書いた記事どおり。
『KDPの価格設定、バーゲン?』 2013/1/31
この時と状況が変わったのはiBookstoreやgoogle play books がオープンして「無料で本を公開できる場所が開かれた」ということ。kindleの場合、有料販売しかできなくて、キャンペーンとして「有料販売している本」を期間限定で無料にできるだけ。
ある時期有料のものが、別の時期にキャンペーンで無料というは、わたしは読者に対して(すでに買ってくれた読者に対して)説明するのが難しいと感じている。
なので、作者や作風、作品傾向などを知ってもらう目的のための作品は最初からそのために用意する。無料本は最初から最後まで無料のまま。という方がスッキリ分かりやすいと思う。
例えばこれが該当→ 『日野裕太郎掌編をEPUB3で無料配布』
集客力としてkindleが断トツだからkindleで無料本をやりたいと思うけど、上記したようにうまく説明ができない。iBookstoreやgoogle play booksはストアとして集客できてない。でも、場所は確保できるんだから、後はお前が・おれがガンバレ、だ。kindleの集客力は欲しい、だからといって、自分ではうまく説明できないことをやるのは(大げさだけど)自分ルール破りな感じがして「イヤ」だ。
電子書籍中心の版元は、AppStoreのやり口をそのまま電子書籍でやっているところもある。
最初、意図的に高い定価をつけておいて段階的に下げている。定価がさがるたびに、バーゲン情報を漁っているサイトのアンテナにひっかかって露出が増える。
これはこれでひとつの戦術だろうし、こういうやりかたもあっていいんだろう。
でも。本でこれはどうもしっくりこない、というか、やっぱり読者に対してうまく説明ができない。
ハードカバーがあって文庫があって、古本があって値段が全部違うじゃないかという話もあるけど、本は実体のあるモノだ。形態が違う・劣化度から値段の違いは説明ができる。図書館は別。モノとしての本を所有することにはならないので値段うんぬんじゃないということで説明できるはず。
電子書籍はデータだ。いつまでたっても同じシロモノ。何を根拠に値段を変動させるのか、わたしには説明できない。
それって売り手の都合だけじゃん。と思ってしまう。
ゲームやビデオは新作から始まって、値段が下がって行くよね、という話もある。たしかにその通りで、もしかすると今後電子書籍もそうなっていく、かもしれない。新刊から時間がたったので=鮮度も落ちたので、値段を下げて並べるかというパターン。
ベストセラー本なら鮮度も重要で、もう届く人には届いたし、次のレイヤーに届ける為に値段を下げるかという戦術も重要だろう。そのために、新刊の時に広告宣伝、大々的にプロモーションをかけるマスな世界。
でも、わたしの出しているような同人即売会レベルの露出、部数の個人出版本。はたして鮮度はそんなに重要なことか?それよりもウチの本を買って、後で安くなったり高くなってるのをみてモヤモヤと不信感を持たれるよりは、たとえやせ我慢でも一度つけた値段は動かさない方がその後に繋がるように思う。
売る側の都合で読者に不信感をもたれたら終了だと思っていて、そのために値段はいじらない。
というのが現時点での整理。正しいかどうか・売れるかどうかは別の話(念のため)
[07/21 18:35:25] 追記
上記は、イベントなどで展開されているほかの方々を否定するものではないです。わたしのところの考え方ということで。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」