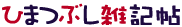- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 300円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 490円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 200円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 600円

- » Kindle
- » iBooks
- » kobo
- » B.W.
- 400円
doncha.net制作・発行:KindleやiBooks、楽天kobo、BOOK☆WALKERで読む電子書籍
個人出版のネットでの読者獲得

読者獲得、集客というやはり200年前から永遠のテーマ。
去年一年で
・kindleやiBookstore、google playなど個人出版が可能な電子書籍ストアが出揃った。
・電子書籍を作るためのハードルは低いので制作することはそれほど問題ではない。
個人出版の作家、タイトルがどっと増えてくる。書き手送り手が増えて、その読者はどこいるの?という状況か。
商業誌だと。
版元に蓄積している売れ行き傾向のそれなりの把握(ターゲットとなる読者像)や取次=書店のデータ(届けるべき読者層)があった。それを雑誌やコミックス、書籍という形の商売にしていた。
リアル書店に新刊を目当てに来る・ぶらっと足を運ぶひとたちは、当たり前の話、「本を買いに・見にくる」ひとたちなので、本を手に取る・購入するモチベーションはそれなりにあるひとたち。
同人誌だと。
そもそも、書き手送り手の思いを共有するひとたちが集まる、というのが同人誌即売会(同人誌を扱っている専門店もある)
常設ではない即売会は、送り手側も読者側もこの機会を逃すわけにはいかないイベント性の高い場所で双方ともモチベーションが高い。
ネットがよくわからないんだよなあ。
いつでもそこにある(アーカイブされている)のがネットの良いところ。即売会のようなイベント性はない。
どこからでもアクセスできるのがネットの良いところ。わざわざ足を運んで書店に行く必要はないし、店に入ったら本だらけという状況もなく、ふと目を外してテレビを見たりお茶を入れたりできる。
今のところ、電子書籍ストアの集客力販売力におんぶに抱っこ。
新刊を継続して出版して積み上げ・広げて読者に発見されるのを待つ。…読者の温度はそれほど高くないのでよほどの幸運が必要で、牧歌的というかのんびりした話(とはいえその幸運を逃さないために継続・積み上げは必須条件、大事大切重要)
個々では認知も進まないだろうから、送り手が集まってレーベル化などでブランディングするのが面白いところだと思う。実際にそういう動きもある。
『日本独立作家同盟』https://www.allianceindependentauthors.jp
『ネット出版部』https://www.facebook.com/groups/125351907617923/
ネットは始めるのが簡単なので、辞めちゃうのもスグ(サービス提供して想定より少ないとはいえユーザーがいるのに投げ出すケースが散見)「ダメだったからやーめた」では根付かないし、読者からの信用も得られなくて、読者の温度も上がらない。「これだからネットは」などと冷えこませることにもなりかねない。
ぜひ頑張ってほしい。
10年以上前、まだ底辺エロ出版社で編集者だった頃の雑記。
『赤字かぁ。。。。』 (2003/11/10)
最初、想定した読者層はどのような属性のひとたちなのか、そのマーケットはまだあるのか、彼らの購買行動に変化はあったのか。
現状の誌面から、どんな読者が買ってるのか・読んでるのか、想像できるかどうか、が全てだ。ここで想像できないようなら今たずさわってる雑誌にはまったく意味がない・売れなくて当然。
独身30歳プラマイ2歳のサラリーマンで月給がぎりぎり手取り20万。彼女とは去年別れたか、今現在別の女性をターゲットにしてる途中で…とか。
結婚して小学校にあがったばかりの長女と幼稚園の長男。ずっと子供にかかりきりだった女房が少しまた可愛くみえてきて驚いたりするやっぱり30代サラリーマン。ローンもけっこう抱えこんでる…とか。
極端だけど、編集ってのは、読者ひとりひとりの顔が想像できるような本作りをしないとダメなんだよねぇ。
わたしはたくさん休刊、廃刊にした3流なのでエラソなことは言えないけど、ロゴや表紙、判型を変えたり、社内政治で根回ししまくりとかしながらも継続したから、雑誌からの成果物=コミックスなどが産まれてきた。というか成果物が形になるまでジタバタと(バブルの残り香もあって辛抱のきく時代だったけど)
法要で集まってたまにやってくる親戚のオヤジみたいなまとめになるけど。
「継続大事」
です。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」